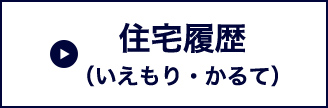災害対応住宅研究委員会Report
2022年度活動計画
全国で毎年のように発生している自然災害等について、大手メーカーや一部の建材・設備メーカーに等の遅れをとることなく災害対応アイディアを建て主に向けて提案できる情報を取りまとめて公表することを目的としている。
昨年度までの2年で災害対応事例の収集と検証を行い、主に新築住宅を提供する際に、工務店として建て主に提供すべき情報やアイディアを取りまとめ、計算や実験などの検証を行い公表を行った。
今年度は、既存住宅のリフォーム等で活用できる災害対応アイディア、被災住宅の改修の効率化を図るアイディアの情報収集と研究を行う。
既存住宅における研究ととりまとめおよび冊子化を15 周年記念大会までに行う。
15 周年記念大会でこれまでの成果である新築・既存版災害対応住宅アイディア集冊子を配布又は頒布。施主にも災害について考えていただけるような冊子にしたので、施主に配布したい会員工務店さんにまとめてご購入いただくという需要が想定でき、頒布も想定している。
委員会開催:奇数月第3水曜日14時開催、11月は15周年記念大会
令和4 年05 月18 日(水) 東京/Zoom アンケート結果の検討
令和4 年07 月20 日(水) 東京/Zoom 災害対応勉強会 アンケート結果のとりまとめ
令和4 年09 月21 日(水) 東京/Zoom 災害対応住宅アイディア集追録下校検討
令和4 年11 月09 日(水) 東京 15周年記念大会 分科会;災害対応住宅アイディア集(新築・既存)版公開
令和5 年01 月19 日(水) 東京/Zoom 次年度の検討
令和5 年03 月15 日(水) 東京/Zoom アンケート等の検討